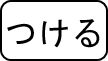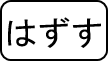校長挨拶
校長挨拶
ようこそ 第二小学校へ
武蔵野市立第二小学校のホームページにアクセスしていただき、ありがとうございます。
令和7年度は、77名の新1年生を迎え、全校児童472名(昨年度比+11名)、17学級(+1学級)でのスタートとなりました。
本校は、明治6年に「栄境学舎」として開校した歴史ある学校です。独歩の森をはじめとする豊かな自然環境に恵まれ、ジャンボリーや親子運動会、どんど焼きなど、地域に根ざした行事が今も受け継がれています。近年では、地域の団体と連携しながら、子どもたちが学校・地域・社会に目を向け、課題を見つけて解決に取り組む「武蔵野市民科」の学びも進めています。
今年度は、武蔵野市教育課題研究開発校(2年次)として、学校風土調査を活用し、子どもたちが安心して学べる学校づくりを進めてまいります。
今後とも、保護者の皆様、地域の皆様、そして同窓生の皆様のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
令和7年4月8日 校長 松原 修
更新日:2026年01月18日 22:13:50